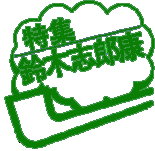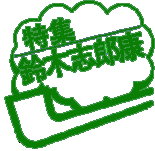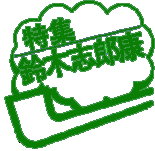
「私性」の語りと方法
高田一彦
四月二七日、日曜日、イメージ・フォーラムにて鈴木志郎康の新作『十五日間』を見る。四日間の上映は作者の新たな展開を示すものとして、これまでのフィルムの相貌との間に大きな差異を意識させ処々にぼくの感情の起伏がひとつの渦に巻き込まれていくことになってしまった。
振り返ると、ぼくの鈴木志郎康の作品との出会いは一九七六年二月の、アンダーグラウンド・シネマテークにおける個展であった。その時に上映された作品は、『日没の印象』『夏休み鬼無里へ行った』『極私的魚眼抜け』『やべみつのり』の四作であった。作者は詩人であり、フィルム作品を語るには
現代詩の理解も必要なのだろうが、ぼくは極めて疎い。フィルム作品からのみ、その辺は探らねばならない。
七七年の大作『草の影を刈る』、七八年の『玉を持つ』までに至る作品群は、個人的生活の中で、撮影するということでひとうの思考が生まれ出て、周囲とのかかわりあいを確かめていくことでひとつの表現を得、伴う存在の拡張、そして根源的有限性の中で満たされうると思うひとつひとつの選択を、塞がれること無さように確かめていく欲求となり、カメラを持ち出す様々な動機というものが「直かに手でさわるようにして知る」という人間のただ生きであることの一面を確かめる作業でもあり得た。
「玉を持つ」は小品ながら、作者のカメラマンを職業とした経験が、風景を撮り続けたことの裏返しをもって、フィティッシュに事物にこだわり続ける姿勢をもつものであったのではないだろうか。そこには、輝く球体をいじることに伴うじれったい程の皮膚感覚があったように思う。
奔放にカメラを持ち出し、生活するものであると同時に撮影するものになるという、自己の触角に親密であるだけ、フィルムに投射されるイメージには、動悸、体温までが視覚化されでもするように真実が生まれる一方、すでに融かされてしまった矛盾を含み続けることともなリ、何度でも新片として捕えられ、眺められる同一の被写体のそれぞれの連動は、時がミシンケイのように単純に経つことに増悪にも似た膨らみを意識しつつ、認識が追い込んでいくことの当然の変節を意識することとなっていくように思う。原因定かでない作者の意固地な、そして防御無ききが如くの性格をそこに感じるのはぼくの自由である。人間であるからには、無器用に、そして躊躇して、そしてある時には理由みつからずに懍ええて、数々のフィルムの断片を印象にとめ、他人には寝返リのように理解不能の意識を獲得することも自由である。
「私は、その断片の映像が、表現になリ変っていく様子を、そのまま映画にしようと考えた。」「私が撮る人々の表情は、私に向けられた表情であり、その表情はとりもなおさず、私自身というもののその空間の中で、存在を示し、それを伝えることになるというのであった。」と、『日没の印象』上映時のチラシに作者は書いている。迅速な時の流れの中で、ぼくのその時の漠然としてしか残っていない記憶をもって、旧い話を書き進めることに恐縮するが……。個人的生活を開いて、そこに漂うものを解こうとし、限られた、もしくは限った時空の中で満されるものとする対象にカメラを向け、やがてスクリーンに映ずるフィルムは「私自身はもう私自身でなくなっている」と言わしめるに至る過程、それは作リ手と観客との予定調和の理解をもっての帰結のみではあリ得ず、重みとなって増殖を遂げたフィルムフィート数が明かすこととなる、得体の知れない存在でもあろう。それは作者の特異性とともに、ある帰属性を含んでいるような気がしてならない。数多く語ることは、その全てが原因に向うような現象である。
リストにあっても上映される機会、もしくは公開を初めからもたない作品も多いようであリ、極私的所以もありそうだ。気付くと、シネマテークで同じ作品を何度か見ていることになる。『景色を過ぎて』はそのような作品だが、その都度新しい発見をするので魅力的な作品である。ゆったりと飾リ気が無く、時には訂正しながらの語りが、その時々のぼくの体調に即し、微妙に印象の度合いが変るからだ。作者の語りは(アフレコであるとはいえ)当然過ぎ去る、ある風景と時間の中の一回切リのものだが、見る側としては何度でも見、開ける。ひとつの「日記映画」を繰リ返し見るということになリ、日付の映し出される映画とは何なのかと、問わずに言われない。形式と内容との完全な共合などは初めから無いのかも知れない。「日付のない目記映画」と呼べそうな作品が数多くあるからである。七十ミリの商業映画も膨大な人間の見えつ隠れつする日記映画であるかもしれない。
『写さない夜』という作品は、カメラを持って自らが撮影できないでいる様子を言い訳でもするかのように、また内的必然性によって展開していく作品だった。他者であるカメラマンが鈴木志郎康を撮影したことにより中途半端な「私」が出たとはいえ、制作意図及び結実すべきところは一人称の作者自身である。重い身体を動かそうとし、撮影へと已れを強いながらもなおかなわず、模索している様子が描かれていく。奇妙な体験だった。絶対的にカメラマンもいるのだが、同時に絶対的に作者もいるのだ。スクリーンに映るあらゆる持続が、その険しい状況にある網目に入っているのだった。
『十五日間』となると、カメラを操作するのは作者であり、被写体も断片的に挿入される作者撮影のそれぞれの異なる場でのシーンがあるが、主なるものは濃密に作者白身の姿である。カメラに向かいその装置を気にしつつしゃべり続ける十五日間の已れに強いる行為。それは発熱に耐え続ける十五日間とでも呼べそうな、均衡を失った時の、ひとつの感覚に襲われ縋る行為のようにも感じる。マイクを持ちながらの重たい沈黙。原稿に向かっていた直後である作者の、何を言おうかと探る仕種はとても切ない。想い浮ぶ言葉を整理しているようで、以外に言うべきことのみを探しているのかも知れない。
その日その日のおもいが、やがて口から出ていく。鬱状態の中で語る時の、やはり切ない眼。原稿を書いていたという、固執したままの、裸の姿勢がスクリーンに映ずる時、観客の安心した位置で見る姿とはとても対極にある。作者は、見えてはならないはずだった秘密の仕切りの中に入り込んでいるかのようだ。観客はスクリーンの中の作者の気分で見ることは当然有り得ず(仮に一人いたとしても、作者をなぞることは不可能故に、己れとは別と、柔らかく他人を装うしかないだろう)、作者の姿は一回ごとのスクリーンの中の現在であり、その痕跡であり、観客は作品に接し得る限りにおいて、一回切りの上映時間の中の場にてのみ現在なのだ。白已のたゆとう感覚のまま、限りなく解き放ちつつスクリーンにあるひとつの行為は、『写さない夜』を見たぼくには予想できたとしても、驚異であった。少なくとも、「相変らず同じことをしているの」と聞かれてしまう貧しいぼくには……。
存在それ自体が構築する世界ででもあるかのように、十五日目に近づいていくにつれ、作者の裸の、膝まで浸った、人間的偶然に近づいていく。不安を感じる程に、かっての作者が持っていた客観的視点が消失している。弱い存在自体となり、沈静したかに見えると、カメラの後に観客を想定した闇の
中の光る目がある、と気付くことになる。事前に気付いであることと思うが……。十五日間の行為による発見、認識とは違うと思うが、その日数で終えることがなぜ必要だったのか……。果して、作者にとり、その時々の閉されてもあるような映像の断片と語りで構成されて良かったものなのか、ぼくは知らない。
『十五目間』は作者を離れ、上映の場で、それぞれの観客の領域で変貌し、増殖を遂げていく様子だ。フィルム中程で始めの部分のラッシュプリントを見ての感慨をのべるシーンがある。『写さない夜』の始めの部分で己れのテープの声を聞き、語り出し、客観的であろうとする行為とは違う。「このままやっていていいものか」という不安が語られるのだ。これは事前にあって当然のことと思うのだが……。フィルムの中に入ってしまった己れの姿にたまらないものを感じ出す。昨日の作者が、今日の作者に迷いこんでしまった、という感じなのだ。己れにだけ向けられる把握は苦悶に似た口調さえ生み出していく。
作られられてしまった作品への新たなる接近は「残された己れの謎」どいう特性への持続をもってより他に方法は無いのではないだろうか。それは当然帰属性を含むものとなる。
作者には、捨象したものが、ぼくにとっては別と、たくさんあると思う。ぼくの迷いこみもこれでいい訳じゃない。ぼくの様々な快楽は作者にはもはや不快なものとなっているのかも知れない。作者の不幸は、ぼくにはまだ真空パックの中の殺菌済の幸せなのかも知れない。ぼくにとっての日常の腹いっぱいの真実が、作者のフィルムの中で、すでに探りあてられてあって解決済の時、確認しながらもついていける時はとても嬉しく思う。それにしても、「私性」を語る映画に残されたものは、己れを撮り、己れの姿を見て語るしかないのだろうか。それは際限無く続けられる行為なのだろうか。
作品にも作者は当然のように属し、作品となる以前の日常にも、鉄筋コンクリートの中に隠れたパイプのように作者は属し、作品以後の緊張のゆるんだ午後の日に照らされる日常にも属す。作者は常に現在にいる。作品を摺ってはいるが、作品以後の作者は、倦むことなく流れる海に向って流れる水のように作品をつくることを繰り返すことでしか作品に属す方法はないのだろうか。裸になろうとしているのか、なってしまったのか、なりたいがなれないのか。それ等全てを被いつくすものは休みなくどこかにあり、やがてやってくるものなのか。
『写きない夜』の始まりと終り近くにミイラの写真集が映される。その苦悶の表情に謎のまま死となってしまった人間を見ようとするのだろうか。ぼくにはわからない。さらけ出すことで肉が付くという保証はどこにもない。そういっている間も無く、裂け目を利用して浸蝕してくるものが数多くある。
『十五日間』を語り、「十五日間を語り」を語り、「十五日間を語りを語り」を語リ……。感情が事物と化しつつあることを想像する。豊饒という虚偽の水溜はやがて乾く。水が腰まで浸り、やがて鼻まで浸る前に。それは言葉を稲妻のように発して止めた後の、ミイラを形づくるものだろうか。
「フィルムメーカーズ」表紙・目次
「鈴木志郎康映像個展」
|HOME|
[曲腰徒歩新聞]
[極点思考]
[いろいろなリンク Links]
[詩作品 Poems](partially English)
[写真 Photos]
[フィルム作品 Films](partially English)
[エッセイ]
[My way of thinking](English)
[急性A型肝炎罹病記]
[変更歴]
[経歴・作品一覧]