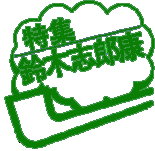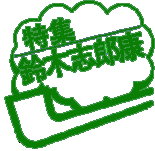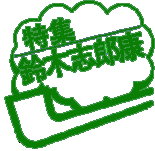
撮ることと撮られことのはざまに
──『十五日間』をめぐって
上野昂志
たとえば、かりにわたしがカメラを廻わしていたとしたら、『十五日間』という映画はいまとはずいぶん違ったかたちになっていたであろう。といっても、何もそれは、わたしが自分の意志で撮るという意味ではない。シチュエーションも何もそのままで、わたしは純粋にカメラを廻わす役をはたすだけの場合にも、ということである。それだけでも『十五日間』は変わっていたはずである。むろんその場合のわたしというのは、べつにこのわたしに限ったことでなく、鈴木志郎康以外のだれか他の人という意味である。
おそらく、そういう誰かがいて、カメラを覗いたリしながら、被写体である鈴木志郎康に向かって、ハイ、いいですか、いきますよ、といったような声をかけたりしながら、一日に五分間の撮影を続けていったとしたら、映画の出来上リは変っていたはずである。たぶん鈴木志郎康は、いまのように、十五日間のなかばを、カメラに背を向けるようにしてはいなかったと思われるのだ。喋ることばはそのままでも、撮られる姿勢は違って、もっと真正面でカメラに正対したであろうという気がするのでる。つまり、その場合には、彼は被写体であることに徹していただろうということだ。
実際の『十五日間』における鈴木志郎康の恥かしそうな姿勢は、撮られるという被写体の位置からきているように見えるかもしれないが、決してそうではない。むしろ、撮る意識を先行させたところで撮られる位置に座っていることからきているのだ。自分で自分を覗きみるということが、彼を落ちつかなくさせているのである。どれほどの恥かしがリ屋であっても、撮られるだけなら、そこで被写体であることを引き受けてしまうであろう。恥かしさは、その写真なり映画なりが出来てそれを見るときにやってくる。ところが、自分でカメラをセツトして、無人のカメラの前に座る鈴木志郎康の場合は、撮る過程でそれにぶつかっていたのだ。見ることをあらかじめ繰りこんだところで見られること。そこで感じられる恥かしさ。ここには、微妙な問題がある。
あの感動的な大作『草の影を刈る』においても、鈴木志郎康は「撮る」ことを問題にしていた。日常のなかにいて、「日常」を撮ること。いま現に日常を生きながら、その生きられつつある時空をカメラに収めてしまうこと。そこからすれぱ、『十五日間』は、カメラを向ける対象を、漠然たる日常から鈴木志郎康という「私」個人に絞りこんだところで作られたといえよう。対象を限定していったところでおのずからそこに行き当ったということだ。しかし、『草の影を刈る』において作者の意識に絶えず問題になっていたのは、日常のなかでカメラを持ちだすとはどういうことか、という点であった。
是非とも撮らねぱならないものがあるわけではない、しかも生活の側からすれば、カメラなど持ちださないほうが自然であるという状況のなかで、「撮る」とは何なのかということが問題だったのだ。それは、また、詩作において、日常の外に出るのではなく日常を降リてきた七〇年代以降の鈴木志郎康にとって、「高く」という行為を問うことにも重なっていたはずである。
ともあれ、とリあえずはそのような自問自答のなかで持ちだされたカメラは、鈴木志郎康の日常を対象的にとらえつつ、それを匿名の生活空間へととき放っていったのである。作者の意識は「撮る」ことをめぐってあったとしても、出来上った映画はそれを明らかにしたというよりは、むしろ、「日常」という観念を無化する方向で日常生活を顕在化したのだ。そのなかで、鈴木志郎康が、日常をかくあらしめている「私」というものに、あらためて執着していったとしても不思議はない。実際「「私」とは、そうやってみる限りは謎だからだ。そこで「私」に焦点を絞ってカメラを向けてみる。
『十五日間』の前の作品『写さない夜』を見ていれば、この推移を具体的に逃れたはずだが、残念ながらわたしは見ていない。しかし鈴木志郎康自身が、それを評して、「他人に撮ってもらったというところに、どっちつかずの『私』が出てしまったのだろう」といっていることは、おそらくその通りだったと思う(『イメージ・フォーラム』314)。『十五日間』から想像してよくわかるのである。「どっちつかず」というより、いかにもそれらしい「私」が、そこに映っていただろうと思うのである。カメラを覗く他人の存在が、鈴木をして、被写体の位置を受けいれさせるからである。そして、俗にドキュメンタリーといわれる映像がとらえる誰かれの姿というものは、多かれ少なかれ、そのような他人を介してのひとつの「像」にすぎないのである。
だが、それならば、他人を介在させないで撮る自分に、これとは異なる「私」がとらえられるのかといえぱ、そんなことはないのである。『十五日間』はそれを明らかにしてしまったのだ。おそらくは、「どっちつかずの私」でない「私」を、いってみれば裸形の「私」をとらえようとして始められたであろう『十五日間』は、逆に、そのことの不在を明らかにしてしまったのである。そこに顕在化したのは「私」ではなく、むしろ「撮る」ということだったのだ。いや、より正確には、「撮る」ことと「撮られる」ことの微妙な関わりだったのである。
鈴木志郎康は、この映画のなかで、やがてカメラと正対するようになるが、そのとき彼は、カメラの向うにはたんに闇が拡がっているのではなく、「観客」がいるのだということをいう。彼は、いってみれば「観客」の存在を発見することによってようやくカメラを直視できるようになっ・だというわけだ。しかし、本当のことをいえば、それは実体としての観客ということではない。そんなものは何処にもいないのである。彼はただ「観客」ということを意識にのぼせることで、「見られる」という位置を受けいれたにすぎない。だが、「見る」ことを先行させたところかち「見られる」ものとしての「私」を実体として措定させた──そのような意識からすれば、ここには明らかにひとつの転移が起こっているのである。それは決して、誰か他人に撮ってもらう、見られるということでは明らかにならないことなのだ。あくまでも、自分で自分を撮るという虚構を設定することによって、その虚構の崩壊を経験するなかで顕在化したことなのである。見ることが、見られるということを抜きにしてはあり得ないように、撮ることもまた、それだけでは孤立的に存在する行為ではない。というよりも、撮ると撮られるとの相互的な関係によってのみ、撮るという行為があるのだ。主体は場にあって、撮る人間にあるのではない。「私」もまたその場とともにあるのであって、それ自体によいささかも謎はないのである。鈴木志郎康は、きわめて簡素な装置によってそれを明らかにしたのである。
「フィルムメーカーズ」表紙・目次
「鈴木志郎康映像個展」
|HOME|
[曲腰徒歩新聞]
[極点思考]
[いろいろなリンク Links]
[詩作品 Poems](partially English)
[写真 Photos]
[フィルム作品 Films](partially English)
[エッセイ]
[My way of thinking](English)
[急性A型肝炎罹病記]
[変更歴]
[経歴・作品一覧]