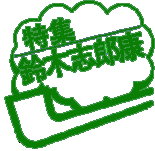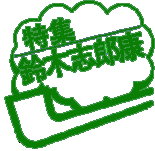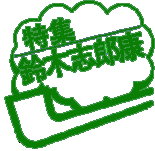
ある日記映画の手触り
居田伊佐雄
『十五日間』の冒頭の数日間は、作者はカメラに背を向けて座っている。時々覗き込むようにカメラを振り返るのだが、その姿が追い込まれた動物のように見える。
前作の『写さない夜』では、「映画を撮ることが出来ない」、と自ら語る事が映画になっていた。「劇映画を撮ることが出来ない」、という意味ではないだろう。劇映画を撮る事は、作者にとって金銭的に問題があるばかりではなく、それが作者にとっての本当に撮りたい映画なのかどうかも疑問なのだろう。映画が劇映画である必然も、ドキュメンタリー映画である必然も感じられず、映画というものの実体について考えあぐねている、そのような状態に思えた。
今回の『十五日間』は、作者が十五日間毎晩、カメラに向かって話をするという設定である。
同時録音用のカメラを、フィルムが終るまで回したままにしておく。映画を撮っていると言える状態なのだが、カメラの前には作者しか居ない。映画を撮っている状態に対する作者の意識が、いかに冴えてゆくか、という事を試しているのだと思った。「映画を撮る事が出来ない」という状態を突破する為の試みなのだろうと思った。カメラの前の作者の姿が、追い込まれた動物のように見えたのは、「映画
を撮る事が出来ない」と毎晩言い続けるわけにはいかない、進退極まる状態に、自らを追い込んでいると思ったからだ。
ところが、追い込まれた動物のように見える作者の姿が、実は計算された演技なのかも知れないと思える瞬間がある。
カメラに背を向けて座っている作者が、覗き込むようにカメラを振リ返るのは、フィルムの残量が気になるからだ。
「そろそろフィルムが終るはずだ」、と言っているうちに、フィルムが終り、スクリーンに映し出されていたそのカットも終る。
あるいは、「こんなことじゃいけない」と言って、俄に攻撃的な様子になった作者が、カメラを手にして、作者を撮影しているカメラを撮影する。スクリーンには、カメラを構えた作者の姿が映し出されているが、それは作者に撮影されているカメラが撮影した映像だからだ。
作者の手にあるカメラが撮影した映像は、次のカットに繋がれている。作者の前に据えられた同時録音用のカメラと、その周囲の室内が写っている。
作者がこちらを振リ向いたとしても、それはカメラを振り向いたという事だ。又、こちらにカメラを向けたとしても、そこには観客席は写っていない。と書いたら、あたりまえすぎて馬鹿馬鹿しいか。しかし、この二つの場面には、撮影する事と映写される事という、隔てられた時間の開係を、眼に見えるようにしようとする計算が、読み取れるように思う。
それが予め計算されていた演技であるのかどうかは、判断する必要はないだろう。映画を撮っているという状態の中で、作者の意識が冴えていったのだとしても、この二つの場面からは、隔てられた時間の関係に、確実に係わろうとしている作者の姿勢が読み取れる、という書になるからだ。
いずれにしても隔てられた時間の関係を貫き通す、意識の手触リを確認するまで映画と格闘してみせた、作者の粘リ強さと頭の冴え具合は相当なもので、なかなかの見物だった。
ここまで書いてきて、読み返してみると、まるで日記映画について書いてあるとは思えない。しかし日記映画の映画である部分に、深く係わらざるを得なかったのがこの映画であって、ぼくの見方が偏っているというわけでもないだろう。
「フィルムメーカーズ」表紙・目次
「鈴木志郎康映像個展」
|HOME|
[曲腰徒歩新聞]
[極点思考]
[いろいろなリンク Links]
[詩作品 Poems](partially English)
[写真 Photos]
[フィルム作品 Films](partially English)
[エッセイ]
[My way of thinking](English)
[変更歴]
[経歴・作品一覧]