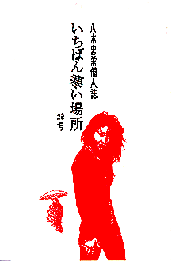花菖蒲人それぞれの誉め言葉
炎天下われら黒々と戦車曳く
炎天や胎児千年をひた眠る
心太ここから先は甲斐の国
訃報くる真昼鶏頭ゆるがざり
ところてん知らぬ女の膝がある
振りかへり犬も行くみち秋の道
*多田道太郎邸での余白句会二句
百日紅やくざ風情がからみあふ
老鴬もまじりて宇治の句会かな
蚊を飼ふてちちはは小さくなりゆけり
人を焼くこの山は蝉泣くばかり
*成田空港にて純子を見送る
「元気でな!」ただ一言の秋わかれ
木下闇よりぬつと出る巨漢(おおおとこ)
*ソウルにて
漢江に哀しき唄の浮き沈み
この道は犬に従ふ虎落笛
わが肩に何の用ある赤とんぼ
かくれんぼの鬼はのつぽのひとりつ子
ぬくめ酒宿のおやぢの与太話
月満ちて欠けて野ッ原家ひとつ
寒酒の底にうねるや日本海
師が沈む五右衛門風呂や十二月
さまざまな事ありまして十二月
台所(だいどこ)もうすらに明ける葱の束
着ぶくれて長電話するニキピづら
昨日今日冷えこみますなあ根深汁
訛りある女とつつくや鮟鱇鍋
しばらくは雪に抱かるる欠け地蔵
海を食ふごとく牡蠣食ふ野郎ども
別れ来て落葉けだもの臭きかな
初空に犬の吠え声一直線
松とれてにはかに魚臭き街
酔ふたふりして帰りけりちやんちやんこ
*一月十八日、妻の誕生日
ほろり酔ふ妻五十四の寒椿
崩れゆくああ東京の雪だるま
海鼠には海の思ひ出海の恋
縁側の小さき日溜り猫仔猫
パソコンと向きあぶだけの春阿呆
父さんの留守にぎやかな雛まつり
寒きもの浜にかたむく寺泊
小さき木は小さき芽をもつ春の山
花の下ゆれてぼやけてはげあたま
花の下亡霊どもの舞ひ踊り
*雄介、鎖骨の手術
桜散る闇に鎖骨をつなぐ音
さくらもち父母の年齢(とし)吾子の年齢(とし)
タンポポはそこまで飛んで日暮れけり
此処からは地獄極楽春おぼろ
板前の庖丁するどき初鰹
頑固なるわが師も今日の衣替
子を育てあげて艶あり衣更
森のうへ雲のうへにも裸んぼ
大あくびもう帰ろうや遠花火
曼珠沙華この道闇へつづく道
をどりの輸ちみまうりやうの影ばかり
逃げて行く女の子赤唐辛子
住職も腰あげにけり盆踊り
故郷(くに)の酒冷やして夏の客四人
唐辛子母のたよりを読みかへす
十月の本郷通りいなり寿司
十月のをんな名もなき乳房もつ
コスモスの色を散らして馬帰る
*いちばん寒い場所から……
・またまた慾りずに俳句特集第三弾。昨年六月から本年九月までに
作ったなかから選んでみた。ただただ手前勝手に「選んでみた」し
だいでありまする。
・私は夏目漱石の俳句を好む。漱石は甘党で下戸だったそうだ。に
もかかわらず酒にまつわる俳句が多いというのは、いかにも愉快。
飲む事一斗白菊折つて舞はん哉
明月や無筆なれども酒は呑む
・いま俳句ブームだという。長谷川格さんが「声の変容」という加
藤楸邨についての論考のなかで、「俳句はいま技の時代である。/
型があり技術があれば俳句はできると多くの人が信じている」と書
き、「技の時代は『うまい句』はたくさんころがっているが、『い
い句』には滅多に出会えない時代でもある。『うまい句』は必ずし
も『いい句』ではない」と書く。虚心に傾聴したいと思う。「句」
を「詩」と入れ替えてみてもいい。己れの地声やかけがえのない生
を棚上げして、知や技術を器用に駆使してみせたどころで、その句
や詩から生きた息づかいは簡単に伝わってはこない。
|