1997年3月26日
多摩美二部芸術学科の卒業生に話したこと。
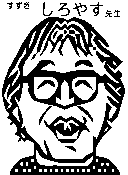
昨日3月25日、多摩美術大学美術学部二部の卒業式があった。わたしはそこの教員の一人として、同僚とともに壇上に座った。1年に2回、卒業式と入学式にしか着ない背広を着て。学長、理事長、学部長、教員代表といった人たちの姿を横から眺めて、話を聞く。皆さん、一生懸命考えてきて話されてる。わたしは、こういう式って、何だろう、と学生気分になってぼんやりと考える。学生気分になったのは、学生時代に愛読したアルチュール・ランボーの名を、学長が引き合いに出したからだ。
学長は「ヴィジオネール(予見者)」なんてことを言ってる。理事長は、「21世紀」なんて言ってる。学部長は「人間関係」なんてことを。教員代表は、「芸術の真の心」なんてことを。わたしは、三題話か何ぞの様に、それらの言葉を結んだり解いたりしていた。それから、教室に行って、卒業生たちに卒業証書を伝達しなければならない。そこで、わたしも何か一言もっともらしいことを話さなければならないと気がついた。
何も考えて来ていない。仕方がない、壇上で思いついた四題話で行こうと思い切った。
式とはなんだろう。ステップだ、といいながら、大学の名を口にし、卒業生の名を呼ぶ。それは、大学を対象化して全体を認識することだ。「20世紀が終わり21世紀が来る」と言えば、20世紀を対象化して全体と捉えようとしていることだ。ヴィジオネールの見地に立てば、20世紀は世界中が「もの」を作って売って儲けようとする激烈な争いの時代だった。21世紀はどうか。21世紀は「言葉」を作って売り争う時代ではないか。
コンピュータは、歯車の代わりに「ことば」を噛み合わせて動かす器械だ。インターネットは、情報という「ことば」のやり取りですべてを済ましてしまう交通網だ。そこでは「もの」は「ことば」に従うだけだ。すでに、OSということばの処理装置の販売合戦では激烈な争いが行われている。ことばを制するものが勝利者になる。それは、コンピュータの業界だけではない。そのことを、心に留めて置いてくださいね。という話にした。そこで、その後、わたしは、「ことば」の争いで起こる戦争は、「もの」の争いで起こる戦争よりはるかに悲惨なものになるということを言い忘れたのに気がついたのだった。壇上のぼんやりが尾を引いていた。
その後、夕方から渋谷に出て、映像コースの卒業生たちとこじんまりとしたパーティを持った。井野元君が似顔絵を描いて来てくれた。卒業生と話すと、どうしても「これから」という思いが、過去の自分の若い頃と重なる。年取ると自分のことを語りたくなるが、それは避けたいと思う気持ち働く。赤坂離宮にあった国会図書館に連日通い詰めて、バルザックとプルーストの小説を読破した、などと言っても、その小説の中身を殆ど忘れてしまっているのだから、どうしようもない。そんな嘗ての若造とはまったく別のわたしが、ここにいるというわけ。
1997年3月24日
96本の卒業作品を見た。
イメージフォーラム付属映像研究所「第20期卒業制作展」

3月15、16、22、23日の両土日で、今年のイメージフォーラム付属映像研究所の卒業生の作品全部、96本の8ミリ16ミリのフィルムを見た。全くの玉石混淆、見るに耐えないものから現在の若い人の映像表現をくっきりと体現しているものまで、非常にバラエティに富んだものだった。見慣れていなければ、ちょっと辛いところだろうが、わたしとしては、大いに楽しんだ。
一口に言って、想いが身体にまつわりついて出て来たと言えばいいような作品群だ。男も女も、作者自身が裸体で登場してくるという作品がかなりあった。2、30年前なら、裸体の映像といえば欲望とエロティシズムの表現というところであろうが、現在は違って、身体と生理とアクションである。自分の身体をイメージにすることによって、また事物や風景に想いを込めることによって、映像によって自己実現しようというのだ。これらの作品につき会うには、かなりのエネルギーがいるが、一途な思いに相対せるので、とても気持ちがいい。
今年のグランプリ作品は、竹藤佳世作品『骨肉思考』(8ミリフィルム、20分)だった。作者は、妊娠した後に、昨年の4月イメージフォーラム付属映像研究所に入り、お腹の中の赤ちゃんが大きくなって生まれてくるまでの自分を中心に、周囲の人たちの対応や、自分の気持ち変化や不安などを工夫を加えた映像にして表現している。思わず、お母さんになる女性は強い、唸ってしまう。
その他にも、才木浩美作品『ディシプリン』、水上弘作品『恒星日』、漆戸美保作品『纏足の子供』、白川幸司作品『意識さえずり』など何本かの作品は見応えがあった。これらの20数作品が、選抜作品として、5月か6月に、四谷3丁目「イメージフォーラム」で上映されることになっている。これらの作品について詳しく知りたい方は、「イメージフォーラム」にお問い合わせ下さい。
イメージフォーラム:電話03-3357-8023:住所新宿区四谷3-5不動産会館6F
1997年3月9日
小池昌代詩集『永遠に来ないバス』

小池昌代さんから彼女の新しい詩集『永遠に来ないバス』が送られてきた。わたしは小池さんの詩が好きなので、早速読んだ。詩誌「音響家族」や「Mignon」で既に読んでいた詩は再会ということになるが、新鮮な感じで読めた。
水が、透明な管を伝わって流れてくるように、心の動きが伝わってくる。人や、物事に対する感受性の鋭さと深さが、スリルを感じさせる。小説のモデルなった人と直接会っているような気持ちなれる。心の中を見せられたその人を目の前にしているというスリル。人の心の動きは見てはいけないのだけれど、見ないではいられない。それが見られると言う錯覚に陥れる言葉の群れ。
近親者とそれに近い人に対する閾の意味が、微妙に捉えられていることで、そのスリルが活きて来ていると思える。その閾を踏み越えるとか、そこに寄り掛かるとか、そういうこれまでの意味合いとは違う意味合いが、この一群の言葉に露呈されてきている。胎外受精やらクローン動物やらが話題になる世の中だ、人間の関係性が改めて問われている。小池さんの詩集はそれをテーマにしているわけではないが、その辺りから広がる不安を感じ取った人の言葉だと思った。
3月13日 小池さんから詩を掲載してもいいという返事が来たので、表題作と「あとがきにかえて」と添え書きされた作品を紹介します。
永遠に来ないバス 小池昌代 朝、バスを待っていた つつじが咲いている 都営バスはなかなか来ないのだ 三人、四人と待つひとが増えていく 五月のバスはなかなか来ないのだ 首をかなたへ一様に折り曲げて 四人、五人、八時二○分 するとようやくやってくるだろう 橋の向こうからみどりのきれはしが どんどんふくらんでバスになって走ってくる 待ち続けたきつい目をほっとほどいて 五人、六人が停留所へ寄る 六人、七人、首をたれて乗車する 待ち続けたものが来ることはふしぎだ 来ないものを待つことがわたしの仕事だから 乗車したあとにふと気がつくのだ 歩み寄らずに乗り遅れた女が 停留所で、まだ一人、待っているだろう 橋の向こうからせり上がってくる それは、いつか、希望のようなものだった 泥のついたスカートが風にまくれあがり 見送るうちに陽は曇ったり晴れたり そして今日の朝も空へ向かって 挨っぽい町の煙突はのび そこからひきさかれて ただ、明るい次の駅ヘ わたしたちが おとなしく はこばれていく 階段の途中 -- あとがきにかえて アパートの階段を上る途中で、一枚の枯れ葉を見 つけた。まだ盛りの緑色を一部に残しながら、渋い 茶色へとにじんでいく、色の変化がおもしろい。波 打つ葉形にも心をひかれた。 足を止め、見ほれたけれど、拾わずに階段を上り きり、部屋へ入った。 しばらくしてから訪問客があった。近くに住んで いる友人である。そして、 「こんな葉が落ちていたので拾ってきた」 とさきほどの枯れ葉を差し出した。わたしが見置い た一枚だ。あれから何人かが、通ったはずである。 あっとおもったが、その縁のようなものを切らない ようにして、黙って友人から、葉を受け取った。 葉とわたしと友人がかかわってつくられた、この 神秘的な偶然をなんと呼ぼうか。わたしは葉でなく て、その葉がつれてきた空間のようなものをぼんや りみつめた。 友人が帰り、テーブルに置かれたその葉を見てい るうち、今度はこの葉をスケッチしてみようとおも った。静物の上にも、時間はなだらかに流れている が、描くことで、鉛筆が背負っているもうひとつの 時間といつしかまざりあう感触がある。 初めて見たときは、あっ、いい葉だ、と、それだ けをおもったのだったが、描きながら、その印象を くだいていくと、そのひとつひとつはけっしてきれ いなものばかりでないと気づくのもおもしろい。葉 の表面にそばかすのようにとびちった斑点、なまい きにそりかえり、すなおでないかたち、それらがな にかのちからによって、まとめあげられ調和をはた し、目に見つけられ、手ではこばれる。 一枚のカットができあがった。再び訪れた友人が 見つける。 「あ。このあいだの葉」 「そう。このあいだの葉」 するとできあがったその絵のなかを、時間は逆流し て流れ始めるのだ。 友人が腰をまげてその枯れ葉をひろいあげた瞬間。 わたしが見つけたが、通りすぎた瞬間。 枯れ葉が階段に舞い落ちた瞬間。 そこから更に、誰も見ていない、葉が枝を離れる 瞬間がある。 そのときどんな、音がしただろう。
小池昌代詩集『永年に来ないバス』
1997年3月1日発行
発行所:株式会社思潮社
〒162東京都新宿区市ヶ谷砂土原町3-15
電話03-3267-8153
1997年3月8日
CD-ROM「Murakami Saburo Performance
entrance-passage-exit
入口ー通過ー出口」

村上三郎さんのパフォーマンスを集めたCD-ROMが、制作者の永原康史さんから送られてきて、夢中になって見てしまった。夢中になって、CD-ROMを見るなんて、久しぶりのこと。面白いのだ。村上さんのパフォーマンスは、枠に紙を貼って、それにからだごとぶつかって、突き破って通り抜けるという単純なものだ。それを40年間、いろいろなところで繰り返していたというのに、心が動かされる。しかも、このCD-ROMの制作の途中で、昨年の1月に70歳で亡くなられたというのだ。制作に当たった永原さんは「一番出来上がりを楽しみにしてくださっていたご本人に見てもらえなかったことが一番残念です」と語ってくれた。
子供が襖をやぶって通り抜けたのを見て、面白いと思って始めたという。その子供の無垢な心を失うことなく続けてきたというわけであろう。ディスプレイの中の小さな画面で見ても、はらはらどきどきさせられるところが伝わってくる。不思議だ。わたしも、そう言うようなことに夢中になっていたいという気持ちになった。このCD-ROMで一つの出会いが持てた。

1956年10月10日
とにかく、最近は説教臭い言辞が飛び交って、わたし自身うかうかしていると、若い連中を相手に説教をたれているという体たらくに陥りがち。それが非常に鬱陶しく感じられているときだけに、村上さんのパフォーマンスは気持ちよく感じられたのだった。

写真の使用については、制作者・永原康史氏におことわりしてあります。
「Murakami Saburo Performance
entrance-passage-exit
入口ー通過ー出口」
1955年から1994年まで全34回のパフォーマンスを完全収録。メイキング・ビデオ、撮り下ろしインタヴュー、詳細年表、著述、紙破りパフォーマンスの全貌を記録。パフォーマンスのフリップブック、実際に破った金色のクラフト紙付き。限定1000部。Published by FLIP BOOKS
c/o Hanjo hanagata hompo Inc. 6F Miyamaru bldg 4-11-23 Minamisemba, Chuo-ku, Osaka 542 Japan
flipbooks@nna.so-net.or.jp