1997年12月31日
立て替えられた亀戸の兄の家。
 「鈴木セトモノ店」は 「マツモトキヨシ」になった。 |
 この視点から「亀戸十三間通り」を 見たのは、生まれて初めてのこと。 |
昨年の暮れは、閉店大売り出しが済んだ後の「鈴木セトモノ店」を訪れて、わたしが育った家が取り壊されると、兄から聞いて衝撃を受けたのだったが、この暮れは、訪ねてみると、家は立て替えられて、一階の店は「マツモチキヨシ」という薬の販売店になっていて、兄たちはエレベータで上った3階に住んでいた。
わたしにとって、若い頃の過去の風景をそのまま現実に見るということはできなくなった。亀戸で、わたしの子供の頃にあったものはお寺の墓石しかない。生きている人間も年上の人は少なくなったが、それ以上に建物が無くなるというのは、そこに住んでいた人のことも語れなくなる。さびしい。70近い兄との会話は、どうしても「未だあの人生きてる?」なんていうものになってしまう。自分も「終わり」に近づいているというわけだ。
時代は変わっていくのだなあ、という実感が今年の秋以後、ひしひしと身に迫って来た。これが、わたしが30代の人間なら、別の時代が始まると大いに気分も高まるということもあろうが、60歳を過ぎてしまっていると、「まだまだ」といっても、「もう終わりだ」といっても、自然な姿勢を取っているとは映らない。気分は結構若いつもりでも、身体がいうことを聞かなくなっているのがいけないのだ。身体と折り合いをつけながら、21世紀を迎えるなんておもしろくないね。でも、年齢ってそういうものなんですね。
わたしの考え方として、身体との折り合いということは一応あるにしても、代わりに妙に頭が軽く冴えてくるという辺りに、自分をシフトさせることで、死ぬまでの期間を乗り切れるのではないかということ。俗いう「枯れる」とは違ったしなやかに「軽く冴える」ということの中身とやり方が問題。それを来年は目標に掲げることにしよう。
1997年12月21日
カニサボテンの花が咲く。
 |
カニサボテンの花が咲いた。部屋の中に置いてある植物は、必ず花が咲くとは限らない。手入れが滅茶苦茶だということもあろうが、人の気配に影響されて、花を開く条件がずれるためかもしれない。とにかく、咲くとうれしい。鉢が足下に置いてあるので、足に触って落ちた蕾を杯に入れてテーブルの上に置いたのも開いた。
この十日あまりは、何ということなく慌ただしい気分で過ぎた。50歳を越えた知人と60歳を越えた知人が二人とも20代と30代前半の女性と結婚するという話、また多摩美の教え子が二組結婚するという話、兄のところに行くとそこの息子が離婚するという話、ある会合では私が2番目の年長者になっていたということ、先週見た秋元松代作蜷川幸雄・釜紹人演出「常陸坊海尊」には集団疎開の児童といたこが取り上げられていたが、実はわたしは孤児にはならなかったが50年前の疎開児童だったということ、これらのことに、ほとんど日替わりで意識の切り替えをしなければならなかった。
そして、一昨日、常用しているPowerMac8500/120でWebを歩き回っているとき、容量の大きいサイトでNetscapeが突然終了するという事態が起こった。行く先々でNetscapeが終了するという事態。そして、OCRのMacReaderProを起動しようとしたら、それも開けない。MacOS7.6.1だったので、いよいよOS8にする時かと、MacintoshHDにインストールしようとしたら途中でインストーラが終了してしまうのだった。Norton Utilitiesで修復して、新規インストールということになった。そのため、インターネット関係やスキャナ関係などの設定を全部やり直すということになったのだった。やれやれ、というところで、疲れた。来週は、近畿大学で現代詩についての5日間の集中講義に行きます。
1997年12月11日
小林泰子詩集『光の木』を読んだ。
 |
小林泰子さんは以前「飾粽」という同人誌で一緒だった。詩人の渡辺洋さんと結婚して、今は二児の母親。この詩集は、小林泰子さんが子供を生んで育てたということが基になっているが、 その内容は子育てとは全く違う方向へ、女性という自覚の意識が伸びていっているところが、面白いと思った。一言でいうと、「野生の芽」を伸ばして行っていると受け止められたということ。
この場合の「野生」というのは、誰でも人間は生まれ落ちると直ぐに教育され「人間」にされて行くが、そういう人間も他の動物や植物と同様に生物として生きて行くわけだが、その生物的な側面をどう自覚するかというところが、いつまでも残されて行く、その意識の領域を指して「野生」といってみた。その領域を「汚らわしい」とか、「無知で清らかな」とか、いろいろと言う人がいる。「詩」というものは、書く人に取っては、自分の「冒すべからざる」領域を言葉で作っていくという側面があるから、当然、その領域を詩の言葉が切り開いて行くところとする詩人もいる。小林泰子さんがそういう傾向を独自な仕方で探していることを、この詩集ははっきりと示している。
詩集の最初に扉の言葉のように置かれた詩、
ここに、その道筋の発端が示されてる。絵本などに見かけるイメージが語られているわけだが、こどもたちの頭を「光の木」の実にしてしまったところに、詩人の自己探索の強い意志を感じさせられる。光の木に こどもたちの頭がたわわに実り 風にゆれている 瞳をひらいた顔 瞳をとじた顔 ぶつかりあって 鐘のように鳴りひびいている
ページをめくった次の詩は、「夕暮れの町」という題で、少年少女たちが庭に埋めた時計から芽が出て、蔓が伸び、町中が時計の木の森になり、その森には少女たちが捨てて行った赤ん坊がすやすやと眠り、時計の木は花を咲かせるというような「話し」が散文で書かれている。どの詩も、詩人が想像力を伸ばして、この世に存在しない植物や動物を生み出して、自分の中に潜む「野生」をイメージによって実現している。そして、自分が紡ぎだしたイメージで包まれたところに、「自然」が戻ってくるという具合になっている。
つき、ひかり、そしてひびき ここに世界がある 十月の蜘蛛はおもった わたしがはりめぐらせた銀の糸に 光りがぶらさがってあそんでいる タべの雨粒が光りを吸ってかがやいている せかいのかけらが こなごなにくだかれて 網目模様のあちこちに飾りつけられ ゆすぶる秋の風に 見えない色をこぼしている 小さなハエが羽音をたててやってくると かがやく糸に捕らわれてもがいている 蜘蛛はゆっくり動き出す タ まだうごめいているアゲハチョウの目に 紅い炎がまたたいた ああ うつくしい と蜘蛛はおもう 空のはしで燃える炎は この目といっしょにわたしの体にはいり しばらくあかるく燃えつづけるにちがいない 蜘蛛はしずかに顎を動かす 夜 すでにこときれて長いトンボの目に 三日月のするどい鎌のかたちが映っている ふしぎなまるでわたしを切りさくようなかたち わたしの体にしまわれた糸をたちきって なにかが始まるにちがいない それはもう始まっている そばでは 不思議な音をたてる虫たちが しきりに羽根をこすりあわせている 雌蜘蛛は背中に雄蜘蛛を乗せながら 風とはちがう空気のふるえを感じていた 音はねばつく糸に捕らわれることなく 周囲をひたしている 美しい音をかなでる虫を食べても 歌は生まれなかった からだの奥にたたまれたひびきは いつか放たれるわたしの歌 あすの朝 卵を産みにいこう そうしたらまた風にのって 冬を越せる場所をさがそう 糸を吹きながしながら飛ぶわたしから きっとあのひびきがこぼれおちる 光りの道筋が縦横にはしっている空 いつかの朝 わたしがいなくなっても 銀色の巣には世界のかけらがぶらさがっているだろうか それを食すのは わたしでも わたしの子どもらでもない この世界をなめつくす 大きな風の舌
これは詩集の最後の詩。二児を育てたお母さんが、詩人と重なって、宇宙的な世界の語り手となっているというわけです。
小林泰子詩集『光の木』・発行・書肆山田
小林泰子詩集『湖上』・発行・すみれ文庫
1997年12月2日
「ローバーと・フランク写真展・Souvenir from Mabou」を見た。
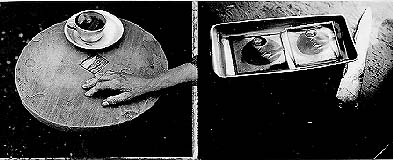 |
四谷2丁目のイメージフォーラム付属映像研究所教室のAクラスの「卒制企画講評」に行く前に、四谷3丁目のギャラリー・モール に立ち寄って、12月1日から27日まで開かれている『ロバート・フランク写真展・Souvenir from Mabou』を見た。10点余りの写真が展示されていた。見ていくうちに、ピアノの小曲集を聞いているような気分になった。写真家が身の回りのものに目を止めて、それを撮影したというような作品が並んでいるが、そういう小さなものや何でもない情景を慈しむ気持ちが伝わってくるのだった。写真って、撮った人の心を伝えるものだ。ロバート・フランクの心は透明で、懐かしい。こういう写真が撮れるって、いいなあ、と思った。
中年のレインコートの男と並ぶようにして見ていたら、画廊の主人の津田さんが来て、その男性と久しぶり!、という挨拶をしている。紹介されたら、津田さんの北海道の郷里の幼友達だった。偶々東京に来て立ち寄ったということだった。津田さんは、この展覧会の準備のために、9月にマブウのロバート・フランクの家を訪ねたときの写真を出してきて見せてくれた。津田さんが薪を割っているところやロバート・フランクと肩を並べて撮った写真があった。その時のことを語る嬉しいそうな津田さん。その親密な雰囲気が画廊の中に拡がった。楽しいひとときだった。