
パソコンを使ってのDV編集コーナー

「極私的にEBIZUKA」のめくれるタイトル

トップシーンの海老塚さん
「極私的にEBIZUKA」の編集。
 パソコンを使ってのDV編集コーナー |
 「極私的にEBIZUKA」のめくれるタイトル |
 トップシーンの海老塚さん |
前の「曲腰徒歩新聞」のアップデートから10日経ってしまった。この間に、身の回りにいろんなことがあった。先週の末に一泊で生駒市に行って、知人の家で、お饅頭の円い下敷きの経木の切れ端を誤飲してしまい、一日絶食した末に近大奈良病院に駆けつけて、レントゲンを撮り、更に胃カメラで調べて、見あたらないと診断され、結局は現在に至るまでに、いつの間にか排泄されたらしいというようなことことがあった。薄い経木だから何のことはないと思っていたが、誤飲後しばらくして、急に激しい吐き気に襲われたりしたので、老人の身を自覚して病院に行ったのだった。その前後に、映像作品「極私的にEBIZUKA」の編集に掛かり、「イメージフォーラム・フェスティバル」にエントリーして、現在も編集中。
「極私的にEBIZUKA」は、昨年、海老塚耕一さんの彫刻作品を瀬戸内海の島に行ったりして撮影した映像を素材にして、映像による「海老塚耕一論」をやってみようという作品。とは言っても、「論」じるところまでは行かず、わたしの得意の「極私的な語り」で海老塚耕一さんについて語るということになる。しかし、海老塚さんの作品に触れて、結構考えたから、うまくその考えを語ることができればいいと思っている。撮り始めた時は、16ミリフィルムで作る積もりだったが、撮影に一緒に持って行ったDVカメラで撮った映像の方が活きているので、DVをパソコンで編集して、それを16ミリフィルムにキネコして、最終的には16ミリフィルムで上映するということにした。
DVで編集して「作品」にするのは、今回が初めて。実は、この16ミリからDVに切り替えるのには随分迷い、ある意味では、これまで16ミリフィルムを主にして来たわたしの映像表現にとっては決定的なことでもあった。撮影した16ミリフィルムのラッシュを見て、どうもしっくり来ない。彫刻作品を撮影するのに、16ミリだとどうしてもカットで撮ってしまう。それが、視覚的な捉え方になる。しかし、海辺とか、山の中とかに置いてある作品に触れる場合、単に見るということではないと感じた。従って、カメラを持って、撮りながら作品に近づいていったり、作品そのものの上に乗ったり、叩いたり、作品の鉄の錆をアップで触るようにして撮影した。つまり、視角だけでなく、全身のアクションで捉えるということになったわけ。そうするのには、片手で持って自在に動き回れるDVカメラがぴったりで、撮影しているのが、わたしなりにダンスをしているようで気持ちがよかった。そういう撮影は、長い間16ミリカメラやスチルカメラで撮影してきたが、今回が初めてだった。その動きの気持ちのよさがうまく伝わればいいがと思っている。
「極私的にEBIZUKA」は映像だけで編集して40分になった。短いDVの編集はこれまでにもやっていたが、40分というのは初めてで、幾つかの躓きがあった。先ず、編集して出力しようとしたら、10分で切れてしまうのだった。これが、ディスプレイの電源の省エネ設定のためと気がつくまでに時間が掛かった。コンピュータは、出力するために編集ソフトのモニターウインドウに映像を表示しているのだから、省エネ設定が働くはずはないと思っていたからだ。ところが、アプリケーションのレイヤーに画像を表示していても、デスクトップにはイベントが起こっていないので、OSの10分という初期省エネ設定が働いてしまったらしい。設定を60分にしたら、40分の出力はOKとなった。もう一つの躓きは、編集にはWindows版の「Premiere5.1」を使っているが、「一時ファイル」の容量がかなり大きいので、読み込んだデータと合わせて、ハードディスクの空きがなくなり編集が出来なくなってしまったこと。プロジェクトファイルを移動すると、リンクのパスがめちゃくちゃになり、データを読み込めなくなる。それで、プロジェクトファイルを作り直さなければならなかった。後は、順調に行った。
編集そのものは、パソコンでやるのは楽だ。フィルムなら現像に出さなければ出来ないディゾルブや文字のダブりも、ただ貼り付けてレンダリングすれば出来てしまう。音楽を付けるのも、ナレーションを入れるのも、フィルムだとダビングルームでキュー出ししなければ出来ないのに、パソコンだと、読み込んだ音楽やナレーションを入れたいところに貼り付ければいいのだ。フィルムだと最低三人は必要なところ、全部一人で出来てしまう。でも、こんな具合に楽に出来てしまうということは、それだけ作品に力が付かないということになるのではないか思う。何処にそれが出てくるのか、ちょっと恐い気ももする。とにかく、あと一日か二日で家での編集は終わる。
詩人の中村葉子さんからのメールが来た。
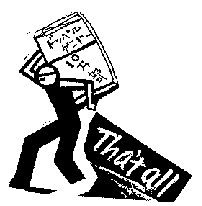 ドッペル10万部 の中村さんの絵 |
1995年頃、「『中村葉子の詩・街頭ばらまき版』と題したビラ(A4両面コピーの詩)を、毎週木曜日の夜中、中野駅ガード下で道行く人に配って」いた若い女性を思い出す方がいるでしょうか。その中村葉子さんから、今年の正月、メールの年賀状を貰った。「Yoko Kogure @ Buffalo」と署名されていた。結婚して、ナイヤガラの滝に近いバッファローという町に住んでいて、インターネットでわたしのホームページを見たいうことだった。当時、中村さんはわたしが講師をしていた「現代詩の教室」に来ていて、そこで彼女に詩に接し、その詩に日常的な意識から抜け出たところがあるのを覚えていた。特に彼女がやっていた「ドッペルゲンガー」という雑誌に載ったお父さんとの会話は強烈な印象を残した。それは最近知らせて貰った中村葉子さんの詩のサイトの「自己紹介」に載っているので読んで見てください。
わたしにとって印象深かったのは、22歳の娘さんが父親に向かって「22才にもなって将来のことを親に訊かれている私とは何ぞやと思いながら私は詩人になります」と言い、父親も「宮沢賢治という人は詩も書いたが働いた」と、応じて「雨ニモ負ケズ」を朗読した、というくだりだった。「詩人になります」という宣言も、可笑しいけど驚いたが、それを諫めるのに、父親が宮沢賢治の詩を朗読したということにも、やはり可笑しかったが驚いた。そこに、詩に対する意識の持ち方が、わたし自身が持っている意識とすっかり変わってしまっているのを実感したのだった。20歳代のわたしにとっても、ある意味で詩は切実なものだったが、生活が全部「詩」に懸かっているという具合ではなかった。22歳の中村さんは「詩」に生活を懸けようというのだ。もちろん現在でもそれは成立しない。そこで、中村さんは詩を書き、行動し、悩んだ。それが中村葉子さんの詩のサイトの詩と散文を読むと生き生きと伝わってくる。
今にして思えば、最近の若い人たちの表現意識のあり方の始まりが中村葉子さん辺りにあったように思える。中村さんが「詩人になります」といった「詩人」は、当時既に「詩人という肩書き」を世間から貰っていたわたし自身の「詩人」とは全く違うものだ。中村さんはわたしと話をしたりしていたのだから、「肩書き詩人」の実体は知っていた筈だ。つまり、中村さんは父親に「詩人になります」といったとき、「肩書き詩人を目指します」と言ったのではなく、もっと本源的な彼女の中で輝いてる「詩人」になりたいと思っていたのだと思う。父親もそれに応じた答をしている。わたしの親なら「馬鹿な」で一蹴していただろう。つまり、中村さん親子の会話は、虚構を現実にやっているように感じられる。「人生」というようなことを前にしたとき、「虚構を演じないではすまさない」事態になっている、ということではないだろうか。「本当のこと」に立ち向かったとき、現実で虚構を演じなければならないことになったら、表現はどうすればいいのだろうか。
敢えて大袈裟に「中村親子の対話」は一つの「表現の事件」だったと捉えるべきではないかと思えてくる。それは、其処にいる筈の「隣の人」がいなかったということが露呈した事件とでも言えばいいだろうか。表現の受け手(読者)としているべき人がいない、ということが顕わになった事件といえよう。わたし自身、両親や兄を自分の読者として考えたことがなかった。そしてそのまま両親は亡くなってしまった。兄には詩集は贈るが感想を聞いたことはない。詩の関係者に認められればいいこととして、別のことのように思ってきた。それが、今の若い人たちの表現意識では違ってきたように思える。彼らには、確かな姿ではないが「隣の人」がいるように思える。一方では、有名になりマスメディアに乗ることも考えているが、先ずは親兄弟を含めて隣の人に向かうということを思っているところがある。(このことは「多摩王」を見た辻和人さんの考察にも述べられている。)ここが大事なのではないかと思う。中村さんからメールを貰って、久し振り!とも思って、何回かメールを遣り取りしているうちに、距離がぐーんと縮まったように感じた。
先日、中村さんのサイトが開かれたという知らせを貰って、覗いたら、最近書いたという詩があった。
家
中村葉子
ずっと向こう側から歩いてきて
霙は降り止まなかった
一筋道を 間違えていた
間違えた道をどれくらい歩いただろうか
引き返すには進みすぎていた
橋の上に立って暗い川をのぞきこむ
冷たい風の突き上がる暗い川をのぞきこむ
壁いっぱい枯れた蔦の覆っている大きな家がある
見たこともないほど大きな家が
表札のない町にいて
詩を書こうと思う
此処ではないことだけが頼りで
塀のない家ばかりが続く
人の声のする方向をふいに見上げると
見知らぬ女性が
私に何か話しかけていた
後ろ向いて指をさしていた
そもそも公道と私道の区別が大きな間違えだった
判っている
判って歩いている
寒い
氷を踏んで
車道脇に積もる雪を避けて大回りしているうちに
霙は雪に変わり 日が暮れようとしていた
雪の多い町では誰も傘をささない
重心が沈んでゆく
その前に
足を踏み出す
氷はなかなか割れない
足を踏み出す
子供の頃の
スケートを想いだす
兄も一緒だった 白いスケートシューズが
はっきりと目の前に見える
わたしにはスケートの経験がない
スケートの思い出を作る
幼児期の幸福
幼児期の幸福
その風を切る
 冬のナイヤガラ瀑布 |  ナイヤガラ公園 |
 バッファロの街 |  鹿の標識 |
「多摩王」の上演上映報告。
 ミュージカル「The Fantasticks」の一場面 |
 映像パフォーマンス 「more more more TV」の一場面 |
多摩美・映像演劇学科の1年生の授業「空間表現基礎」の年度末の発表会用のDMの写真のモデルをやったので、行きがかり上、その発表会の実際に行われて内容を、一応報告しておくことにします。「空間表現基礎」を履修している学生は75人。これを学生一人一人が互いに仲間を選んで7グループに分かれて、そのグループの中で討論して「企画」を決めて制作して上演上映した。制作に使う費用は、実習費から一人いくらと決めて配分して、足りない分は自分たちで出すという方式なので、グループに人数が多くなると制作費も多くなる。ただし、人数の配分が極端にならないように教員がそれなりに案配するという仕方で制作した。その結果、ミュージカルが1つ、映像パフォーマンスが1つ、映像ダンスパフォーマンスが1つ、映像と人形劇を組み合わせたパフォーマンスが1つ、アニメーションが1つ、DVによる映像作品が2つ、ということになった。
ミュージカルはハーヴェイ・シュミット作曲、トム・ジョーンズ作詩・台本の有名な作品「The Fantasticks」を、自分たちなりにこなした上演となっていた。講堂の前の方の座席を数列外して、そこに円形の舞台をしつらえて、舞台上に穴を作って、そこから人物や小道具を出し入れする。話は、隣同士の仲のよい父親、植木屋とボタン職人がそれぞれの息子と娘を結婚させるために、二人の仲に反対して、両家の間に 障害の壁を築き、返って二人の気持ちを煽り、最後は誘拐事件まで引き起こして二人を結ばせるというもの。音楽は学生の一人が初めから終わりまで、ピアノの生演奏で弾き通した。歌やせりふがやや聞き難い点があっても、結構な出来だった。演出はちょっと経験のある社会人学生だが、一年生で殆ど素人の学生たちをよく指導した。3回上演したが、そのうち2回は用意した50席では入りきれず立ち見となった。
映像パフォーマンスは、映像スタジオを使って、周囲を白い布で囲み、ライトで色を付け、正面のスクリーンに都内の六本木あたりの街を行く格好のいい女性の姿と自分たちの姿を映し出し、ハイセンスの女性たちに憧れる気持ちを、実演で語りだそうという作品、題して「moremoremore TV」。最後は、街を歩いて疲れて自分の部屋に帰ってきた若いの女の子の、CDを掛けたり、雑誌をめくったり、コップに氷を入れてコーラを飲むとかいう日常的な仕草で終わるが、このシーンが二人の女の子の部屋が並んで同時進行するように演出されて、雑誌をめくる音、コップの氷の音などが拡大されて聞こえるだけといった具合に仕立てられていた。マイクを仕込んだのではなく、作った音に演者が合わせるというやり方が、新鮮で面白かった。
映像ダンスパフォーマンス「mutton」は演劇スタジオの両側に借りてきたイントレを組み上げて客席を作り、広いフロアの真ん中にスクリーンを吊して二つに区切り、その両方のスペースでそれぞれ三人のダンサーがダンスをするというもの。スクリーンには、別々の映像が別々の方向から映写されて、部分的にスクリーンを透過して、それそれ反対側の映像が見える。投射される映像は、一方が動く円や電線など抽象的な絵柄、一方が頭にカメラをつけて雪の道や公園を走り回り、ブランコに乗ったり歩道橋を駆け下りるといった具象的な映像。それらの映像の前でダンサーは比較的にスタティック身振りで踊っていた。最後はダンサーの影が拡大されてダンサーの身振りにシンクロする。音楽は学生がコンピュータで作った音響を使っていた。格好良さを狙って、それなりに格好よかった。
人形劇「彼女はピーチ・ジョン」とドキュメンタリー・アニメーションと称する「4 ℃のライオン」には、わたしは度肝を抜かれた。
「彼女はピーチ・ジョン」の始まりは8ミリフィルムで、のっぺらぼうの人形がたこ焼きの流れ作業をするシーンから始まる。後で聞いて分かったのだが、それがたこ焼きから蛸を抜く作業をしているというのだった。と、急に人形の足下に雨が降ってきて、如雨露で雨を降らす女の手。実は雪の日、女は歩道橋の上から如雨露で水を撒いていた。そこに、先ほどたこ焼き作業をしていた人形が二つ頭の人形になって現れる。何と、人形は彼女に思いを抱いていたのだ。そこで、恋弁天に願いを掛けて、彼女と擦れ違いざまに蛸の足を渡して、その蛸足の吸盤に魅了された彼女は、二つ頭の人形を受け入れて、抱き合って踊ることになる。そして、何故か分からないが草原を歩いて、8ミリフィルムは終わり、スクリーンが巻き上げられて、彼女と人形の結婚式の実演場面となる。彼女はウエディングドレスを着て、二つの頭ののっぺらぼう人形を抱いて踊っている。踊るうちに人形の一つの頭が転げ落ち、足が落ち、腕が落ち、頭と胴体だけになったところで、天井から風船が降りしきって、彼女は人形を椅子に置き、自分も並んで腰掛けて、キスする瞬間に、人形と彼女共々後ろにひっくり返って、ニョッきっと彼女の二本足がウエディングドレスの中から開いて、足の臑裏に「また来てね、ありがとう」と書いてあるが読める。この奇想天外な人形と彼女の恋の物語は、いったい何だあ、という驚きだった。これは、始めて見た21世紀的表現だ、とわたしは咄嗟に思った。その21世紀というところは、次に紹介する「4 ℃のライオン」と合わせて考えることにする。
「4 ℃のライオン」は、企画提出の段階で「ドキュメンタリー・アニメーション」と銘打って出されたので、先ずはそもそも「ドキュメンタリー・アニメーション」とは何かと問い直さなければいられなかった。説明を聞くと、女の子が小学生の時に山の中でサンショウウオを見て驚いた、その場所を再び訊ねるのをビデオで撮って、それを線描きの15分ほどのアニメーションにするというのだった。15分のアニメって気軽にいうけど、原画を何枚描かなくてならないか知っているの?と聞くと、「はい、7200枚です」とさらっと言ってのけた。一月もないのに、本当に出きるか心配だったが、上映日には、確かに若い女性がグループで小学校を訊ね、村の老人に話を聞き、子どもたちに場所を聞いて、山の森の中に分け入って、サンショウウオがいそうな池を見つけるまでがアニメーションで出来ていた。5000枚余りを書いたりコピーしたりして原画を作ったという。音声はDVで撮影した音声が、絵に合わせて編集されていた。小学校の女の先生の対応や老人の話す様子は見る人たちの笑いを誘った。上出来とは言えないが、ユニークなアニメーション作品といえる。多分類例がないであろう。イメージ優先のアニメを現実に合わせるなんて、というのがわたしの驚きだった。これも、21世紀の表現の萌芽といえよう。
これらの作品の何処にわたしが21世紀の表現を感じているかというところ。それは、「彼女はピーチ・ジョン」も、「4 ℃のライオン」も全体を統括する者がいないで作品が成立してしまったということだ。「彼女はピーチ・ジョン」なら、8ミリをやりたい者、人形劇をやりたい者、実演をやりたい者がそれぞれの思いを実現したということ。「4 ℃のライオン」なら、サンショウウオのいる場所に行ってみたいという者、アニメをやりたいという者、ドキュメンタリーをやりたいという者がそれぞれ相手を否定することなく受け入れて互いに協力して作品を実現した。共同作業の出来ない、気遣いの世代の新しい集団形態が作品を生みだしていると思えた。ことの善し悪しではなく、そういうようなことが現在形で進行しているということ。
発表会の作品はあと、DV作品「大学生≠大学生」と「足をゆらせば」の2本あった。「大学生≠大学生」は大学受験に失敗した男が「大学生クラブ」という大学生の振りをして集まるクラブに入って、連日コンパでビールなど呑んで遊んでいるうちに勉強する気になって再び受験に挑戦するという話。「足をゆらせば」は、身体障害者の振りをして車椅子生活をしている画学生が、サディストの女王様にさいなまれるが、彼の絵を焼いたことで彼女を縛り首にしてしまうという筋書き。一種の怒りの表現だが、映像だけの表現になると一筋縄ではいかないなあ、というのが、感想だった。
ミュージカルを除いては、ほぼ一ヶ月という短い時間内でそれなりの見ること出来るもの作ってしまったのには、毎年ことながら驚く。今年は映像がパフォーマンスへと枠を広げていっているのが目立った。また、わたしのこのホームページの宣伝で詩人の辻和人さんと北爪満喜さんが見に来てくださって、それぞれのホームページで感想を書いてくださっているのでお読み下さい。
辻和人さんの感想「錨」2月5日
北爪満喜さんの感想「Memories」2月8日
2月9日にこの発表会の講評が終わったところで、わたしは悪寒に襲われ、学生たちと打ち上げに行くのを諦め、タクシーで帰宅した。体温計で計ったら39度。それかた三日寝込んで、12日の今日、ようやく熱が下がったのを見計らってこの記事を書いた。麻理さんは「駄目よ、寝てなさい」といっている。
ホームページを開いて丸5年。
 1996年当時の最初のホームページの絵柄 |
ホームページを開いて、1月の半ばで丸5年、2月1日でカウンターも丸5年経った。インターネットに接続したのが1995年の12月20日。19日にcatnetからIPアドレスが送られてきてPC-98のWindows95で接続を試みるが失敗。20日、Macで成功。21日Windowsで再び失敗、Cドライブクラッシュ、システム再インストール。22日「PLUS」をインストールして成功。と、トラブルの連続の果てにようやく安定した接続を得て、1996年の1月16日にホームページ開設。そして2月1日カウンター設定したというわけ。2001年2月2日現在カウント数は62436となっている。Webを始めて、それまで使っていたMacのLC575やPC-98では遅くてかなわないと、1996年2月22日、ソフマップ西新宿店で「Power Macintosh 8500/120」と「NANAO FLEXSCAN 54T」を購入した。847.171円だった。今からするとかなり高価だ。このPowerMac8500にG3カードを差して、今でも使っている。今年辺り、G4を買おうかなあ、と思っているが、MacOSXって大丈夫なのかなと、ちょっと心配だ。
ホームページを開いて、どんどんコンピュータにのめり込んでいったから、生活も代わった。表現意識も変わったと思う。しかし、そこのところはよく分からない。1969年の9月から「曲腰徒歩新聞」を掲載し始めて、そこに文章を毎週書くということが、わたしを変えたと思う。その創刊の1996年9月23日に
この「トボトボ歩いている」という言葉は、今でもわたしの心の中に生きている。世の中には、毎日のように式典に出席して、祝辞を述べてたり、弔辞を読んだりして、それが好きな人もいるが、そういう人とは反対に、わたしはそれが苦手である。晴れがましいところにでは、身体が固まってしまう。それが厭だ。ひとりで勝手にしていたい。歩いていて、見つけたものに夢中なる。時には、結構、興奮もする。こちらからの勝手な出会いが好きなのだ。そんな、他人には無意味な出会いの集積が、わたしの人生とも言えよう。と書いているが、この「他人には無意味な出会いの集積」に情熱を傾けるようになった。それは、一年当たり一万もの訪問者がいたということで支えられた。この数には本当に驚いた。わたしは本を何冊か出しているが、その発行部数はせいぜい1000とか2000で、詩集など500部にも満たない。圧倒的な数の違いだ。この数が本当はどういうものか、わたしにはよく分からない。でも、それを「人数」に置き換えて、実感として受け止めてしまう。虚空に幻想を描いているのかも知れないが、とにかく、実感として受け止めれば、わたし自身は現実の生身を持つものとして、なにがしかの期待を込めて文章を辿るところとなるわけ。それで、意識が変わる。現在、自分の変化を感じながら、それを明確に意識できないでいるというところ。