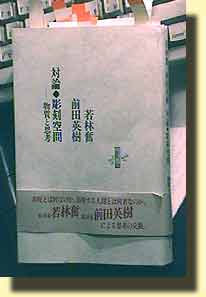
若林奮/前田英樹著『彫刻空間』
若林奮/前田英樹著『彫刻空間』を読んだ。
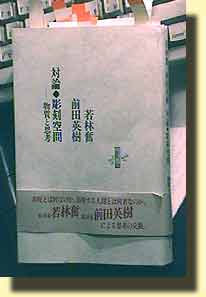 若林奮/前田英樹著『彫刻空間』 |
現在、「山北作業所」というタイトルで彫刻家の海老塚耕一さんの彫刻の制作現場を撮影したビデオ作品を編集しているところ。大方の編集が出来て、これから詰めの作業に入り、ナレーションや音楽を付けるところまで来た。そして、そこでちょっと手を休めて、どういうナレーションを付けるか考えている。昨年刊行された『彫刻空間』という本が目の前にある。彫刻家の若林奮さんと批評家の前田英樹の「対論」を一冊の本に纏めて、昨年の暮れに書肆山田から刊行されたもので、ナレーションを考える上で参考にもなるなあ、と思いながら読んだ。
若林さんの彫刻は好きで、これまでに画廊に展示されたいろいろな作品を見ている。また若林さんにはわたしの詩集の装丁を何冊かしていただいている。前田さんの本は書肆山田の鈴木一民さんから贈られたことがあるが、難しそうな本なので、これまで一冊も読んだことがなかった。前田さんは剣道をやるフランス思想の研究家でもあると聞いている。まあ、若林さんも前田さんも全くの未知の人というわけでない。本を読むというとき、その本への接し方って、微妙な心理が働く。若林さんの個展も最近行ってないなあとか、前田さんの本を以前貰ったけど読んでないなあとか。で、この本を開くまでに時間が掛かった。「山北作業所」を編集しているから、いまがチャンスだという思いも働いて読み始めた。
「対論」という形で言葉が出てくるからか、そこで語られていることに、ある種の了解が前提になっているためか、始めは入りにくいところがあった。前田さんは若林さんの彫刻に対する関心から語り始められるのだが、若林さんは若林さんで自分の鉄という素材についての考えを一方的に語っていて、おのおのが相手を前に自分の関心事を語り相手だけを見ているというような恰好になっている。なるほど、前田さんは剣道をやる人と聞いていたが、これは剣道の試合のような感じだなあと思ったのだった。しかし、相手を倒すというのではない。それとは全く反対に、相手が出す技、ここでは思考に使われる観念ということになるが、それを受け止めて、相手を起立させて行くという展開になっている。相手を生かす剣道っていうようなわけ。互いに緊張しているから、剣がもつれると、まあ観念がもつれてくると、言葉の道筋を見極めないと分からなくなってくるところもある。そこが面白いといえば面白かった。途中から、セザンヌやマチスやジャコメッティやピカソが話題として登場してくるが、その辺に来ると、映画のチャンバラ場面を見ているように爽快な気分になれた。喩えとして適切かどうか分からないが、鎖鎌を使う若林流と長剣を使う前田流の試合といった感じ。その試合の雰囲気は「知性」の対決に居合わせるという感じで非常に刺激的だった。
前田英樹さんは、始めのところで、若林さんの芸術への関心の持ち方として、
もう一つ、私が若林さんの作品を見ていていつも共感する点なんですが、若林さんの作品には作品そのものの外側に在る世界や自然に対する強い信頼がある。そしてその作品の外に在る世界と作品とがいろいろな複雑な通路でつながっている。こういう通路が、作品の外の世界に対する非常に強力で多様な探究の線を創り出している。作品の外に在る世界とつながりを持たない作品は、私にはあまり面白くないんです。たとえば、抽象表現主義みたいなものは私にはつまらない。また、芸術記号のコンポジションだけで自律しているような作品にもあまり興味を持てない。逆に、自然とか社会とかとのっながりをある形で確立しようとする作品、そうした通路の確立が一種の探究であるような作品が私には面白い。彫刻や絵画は外的世界の表象──似姿──であることから手を切って久しいわけですが、しかしそれでも外側の世界と如何につながりを持つか、如何にしてそこに入り込むかという問題は、相変らず一番重要な問題としてあるはずです。そういう問題から離れてしまった作品は、美術界の外にいる私のような人間には面白くなくなってしまうんです。若林さんの作品がいつも私の関心を強く惹く理由は、簡単に言えぱそんなところです。と述べている。
で、依然として個人のことになってしまいますが、私が鉄というものを意識したということの最も初期の段階で言えることは、繰り返しになりますが、「鉄が輝いていた」ということです。そこのところが非常に大事なことだったと思えるんです。正確に言えばその後になって、鉄についてのいろんな大事な経験とかいろんな知識を持ち続けて、鉄の広がりに気付き、鉄の持つ空間というものを考えることができるようになるのですけど、最初の場合の鉄は一瞬のことと言ってもよいくらいのことだと思うんです。何故がと言うと、鉄の輝きに引き込まれること自体が一瞬の出来事であるということと同時に、鉄が生地を出して輝きを表すということは、鉄にとっては非常に不安定な状態であることになるからです。地球上の鉄というのはほとんどが酸素と化合したり硫黄と化合したりした状態にあるわけで、その方が安定している。鉄が鉄であるということの人間にとっての意味は、鉄が純粋であるということ──できるだけ混じりつ気のない鉄であるということだと思うんです。けれど、それに伴って、そういう状態の鉄が大変に不安定なものであるということ、そのまま長く続くことはまずあり得ないということでも鉄を見ることができるわけです。私もそれまでに鉄というものを多く見ていた。だが光を持った鉄、削って中が露出した鉄の輝きというものがあった。その当時、私は鉄をある純粋さの中で捉えようと考えていたし、それがそのまま維持されることも考えるわけです。彫刻としての空間をつくっていく過程の中では、とりあえず、そういう努力をするわけです。しかしすぐ、それはできないことに気付きました。それは鉄だけのことではなくて、別のものを検討してみると、ある程度の安定に向う方向があり、それは私にとってはおそらく何かが失われていく方向なのかも知れません。この辺りが、絵画と違うことの一つなのでしょうか。不安定な状態は、身近に素材・ものを置く者にとっては、常に不安であると同時に、快適なことでもあります。自分自身がそれを何かしらの形で補っていくような事態を生じさせるものもあって、それが彫刻の空間というものに繋がっていくこともあるのではないかと思います。と、まあ鉄を使った彫刻作品の成立の根拠を述べる。ここを出発点として、二人の対論は、芸術の持つ意味合いとその芸術作品の成立を辿るようにして展開して行く。
LinuxとWindowsXPの共存をようやく復旧。
 庭に咲いた水仙の花 |
水仙が咲く季節になった。この半月余り暇があれば、Linuxをインストールしたマシンで起動できなくなったWindowsを復旧しようとあれこれやってきた。そして、ようやく復旧出来た。
先月turbolinux 7を無事インストールした、というところまではよかったが、その後、終了時に暴走するのが気になって、Linuxをインストールし直した際、失敗して同じマシンのWindowsNTとWindowsXPが起動できなくなってしまったのだった。それを復旧させるのに20日間も、あーでもないこーでもないとやっていたというわけ。これから書くことは誰の興味も引かないでしょうね、と思いながら、孤独な気分でご報告ということ。
そもそもTurbolinuxを再インストールした際、「ほとんどの設定が自動的に行われる」という「Turboインストール」というのを選んだのいけなかった。Linuxをフロッピーディスクで起動させていたのに、このインストールの仕方では、IDEのマスターのHDDの「MBR(マスタブートレコーダー)」にLinuxの起動を操作する「LILO」を自動的に入れられてしまったが、具合が悪いことに、これが壊れてしまった。ということは、OSの起動を操作するところが壊れてしまったということで、WindowsもLinuxも起動できなくなったということだ。ここから、あーでもないこーでもないが始まった。
Linuxはフロッピーディスクを使って直ぐにインストールして、起動もフロッピーで出来るようにしたが、WindowsはNTもXPも起動できない。本を読むと、「MBR」のLILOを削除するには、MS-DOSのシステムディスクで起動して、コマンドラインから「fdisk /MBR」で削除できると書いてあった。で、他のマシンでシステムディスクを作り、そこにfdiskをコピーして壊れたLILOを削除しようとしたが、このわたしのマシンは何故かMS-DOSのシステムディスクでは立ち上がってくれないのだった。WindowsNTの「Setupディスク」なら受け付けるので、NTを再インストールすればMBRのLILOは消えるかと、再インストールしてみたが、再起動がかかったところで、壊れたLILOに掴まって止まってその先に行かない。つまり、再起動できないので、完全にインストールするが出来ない。WindowsXPはCD-ROMから起動してインストールするようになっているが、わたしのマシンはCD-ROMでは起動できない。LinuxでLILOを復旧して、LILOからWindowsに起動を切り替えるやり方として、LILOの操作を調整する「lilo.conf」というファイルを書き換えて見るということもやってみたが、Linuxをインストールしたハードディスクと「MBR」があるハードディスクが違うからか、「警告」が出て、それも成功しなかった。つまり、壊れたLILOの為に、にっちもさっちも行かなくなってしまったというわけ。
LILOが削除できれば、Windowsは再インストールして起動できるはずだ。システムディスクで駄目なら、最初からハードディスクをフォーマットすればいいのではないか、と思って、Windows98SEのインストール用の起動ディスクを立ち上げようとしたが、これが駄目。WindowsNTのセットアップ・ディスクだと起動がOKなので、それで立ち上げて、LILOが壊れているハードディスクをフォーマットしてNTをインストールしたが、LILOは壊れたまま残っていて、再起動出来ない。フォーマットしても駄目なら新しいハードディスクを買ってこなければ駄目なのかと思った。いや大事になってしまった。古いマシンだから新しいハードディスクを付けるなんてことしたくない、という気持ちもある。そして数日過ぎて、このマシンはLinux専用のマシンにしようと結論した。もう一度turbolinuxの再々インストールだ。turbolinuxは3GB以上必要だ。2GBのマスターのHDDには先頭にLinuxのブートセクターと/swapパーティションだけを置き、そこにLILOをインストールし、6GBのスレーブのHDDに/rootと/homeのパーティションを切って、インストールした。その時、マスターのHDD、つまりhdaに1.5GBの空きが出来た。そこでまた欲が出てきた。ここにWindowsをインストールできる、そしてlilo.confを書き換えれば、もしかしてWindowsが起動できるかも知れないという思いだ。
どうせ一か八かのインストールならWindowsXPをインストールしたい。CD-ROMでは立ち上がらないが、WindowsXPをフロッピーディスクから立ち上げてインストールするやり方がある筈だと思い、MicrosoftのXPのサイトを見たらあった。ダウンロードして6枚の「Setup Disk」を作る。そして、それがうまく立ち上がった。空いた1.5GBをNTSFにフォーマットしてインストール。途中の再起動で立ち上がるかどうか冷や冷やしたが、LILOが消えていてすんなりと立ち上がり、WindowsXPのインストールに成功したわけ。LILOが消えてしまったが、Linuxはフロッピーディスクで起動できる。これでようやくLinuxとWindowsXPを一つのマシンで共存させることが出来た。TurbolimuxのKDEのデスクトップではやや反応は遅いが、この古いマシンもまだまだ使える。
三木卓さんの『わが青春の詩人たち』を読む。
 三木卓著「わが青春の詩人たち」表紙 |
ほぼ一日で300ページ余りの本を読んだのは久し振りだった。三木卓著『わが青春の詩人たち』は、わたしにとっては面白い本だった。好奇心、あるいは関心が満たされた、といった方が実感に近い。三木卓さんは御存知の小説家、その三木さんが詩を書き始めた1950年代から1960年代に小説家になるまでのおよそ十年間に接した詩人たちの詩と彼らの現実の姿を、詩の組織的な運動に関わり、また読書新聞の記者として接した視点から書いた本だ。わたしが一気に読む気になったのは、この本の終わりの方に、わたしのことも書かれていて、そこにわたしのことを、
「かれは人柄のいい人で、当時のぼくは失業中だし詩の仕事も大いに元気とはいえなかったが、かれは売れっ子風など吹かせたことは一度もなく、いつも楽しく座談できた。あれはかれの友情だった、と思っている。」と書いてくれているので、すっかり嬉しくなってしまったからだった。それに、わたしが知っている詩人たちも沢山登場してくるし、その詩人たちのわたしの知らなかったことも書いてあるので、なるほどそうだったの、という思いもあって、どんどん読んでしまったというわけ。
多摩美・映像演劇学科の発表会いろいろ。
 「SLAVE」 |
 「家政婦は寝た」 |
 校庭の映像パフォーマンス 「world wide wave & the wall」 |
一月の後半から二月に掛けて、多摩美映像演劇学科の2年4年1年の発表会が相次いで、毎日のように舞台上演や映像作品を見て、それに学期末の会議が重なり、そして更に「イメージフォーラムフェスティバル2002」に作品をエントリーするためにビデオ作品『山北作業所』の編集をしていたから、睡眠時間を短くしなければならない忙しさだった。実際、地下鉄の乗るとたちまち睡魔に襲われるという状態だった。そういうわけで、「曲腰徒歩新聞」の更新が飛んでしまいました。愛読者の皆さんにはお詫びしなければなりません。9日の卒業制作の講評を終えて、採点も済み、ようやく一段落した。残るのは2年後の新カリキュラムを決める会議と、大学の最大のイヴェントである三月の一般入学試験。大学教員の生活は結構忙しい。そして、講師をしている「イメージフォーラム付属研究所」の卒展があり、100余りの作品が上映されるというから、これも楽しみだ。
忙しかったけれど、発表会で見た学生たちの作品にはわたしに取って刺激的なものが幾つかあった。それらの作品を見ているうちに、わたしの表現についての考え方が少しずつ変わっていくように感じられた。それは表現には主体があるが、その主体のあり方の問題とでも言ったらいいか。3学年全部の発表会で、身体を使った上演作品が7つ、映像の上映が20作品、パフォーマンスが5つ、写真やオブジェの展示が7つと、合わせて39作品につき合い、しかも、その多くが集団で制作されているのに出会うと、その表現主体というものが個を越えた姿を取っているとように思えてくる。そういう感じがわたしの中に生まれてくる、ということが面白い。
4年生の柿澤友子さんと熊澤彩花さんの作品「SLAVE─身体蘇生装置─」は、訪れた者に自分の身体をいやって言うほど体感させる装置だった。真っ暗にした画廊の床に45センチ四方、深さ70ミリの木枠を64個敷き詰めて、その一つ一つをアクリルの容器として底に鏡を置いたり、水、ワイン、スライム、剣山、ホッカイロ、食パン、しめじ、中国の豆、小豆、油ねんど+くるみ、土+こけ(二種)などを入れて、来た人には裸足になって貰い、ブラックライトで身体にまつわる文字が光る浴衣を羽織らせて、その木枠の上を歩かせる、というものだった。所々の木枠が蛍光灯で光っているが、真っ暗だから何を踏むか分からない。爪先で探って歩くと、ざらざらしたり、ぬるぬるしたり、痛かったりするから、足の裏に神経を集中させることになる。そして、蹠の触覚がむらむらと立ち上がって来るのを感じる。快感だったり、不快だったり、また不安にもなる。とにかく、そこにいる限り、自分の身体の意識から逃れることは出来ない。その意味で、ここに入った誰もが身体の奴隷になるというわけで「SLAVE」という題名なのだろう。
わたしはかなり長い時間そこに滞在した。今でもその触感が記憶に残っている。先ずは暗闇なので、平衡感がおかしくなって、しゃがむような恰好でなければ移動できなくなった。剣山の針に足を乗せたとき非常に痛かったので、そこにどさっと足を乗せないように注意を払った。そして、剣山があると、片足ずつ乗せてみた。痛いけれど気持ちがいいので、しばらく乗せたままにした。足の疲れがとれていくように感じた。しめじは気持ちがよかった。その代わりに足の裏につく食パンは何だ分からずべたべたくっつくので気色悪かった。灯りのついたアクリル板の上に乗ってもいいのに、そしてそこが一番安全なのに、何故か乗るのを避けて、暗い危険な木枠に足を置いてしまうのだった。64個の木枠全部を踏むことはなかったが、二巡りして外に出た。画廊を出ると非常に爽快な気分で開放感があった。
1年生の川田夏美さん、中林舞さん、丹羽良徳君、藤谷香子さん、吉井裕子さん、石田亮介君たちがやった「家政婦は寝た」というパフォーマンスは、身体を問題にしているが、挑戦的な柿澤さんたちとは違って、全くの受け身によって自分たちが耐えるという仕方で身体をまるまる体感するというものだった。小さな教室の一室に350本の古タイヤをばらばらに積み上げて、そこに外から3センチ幅の細長いゴムを引き入れて、タイヤといわず窓枠といわず搦めて、更にタイヤの上に倒れた自分たちの手足胴体首に搦めて自ら動けないような状態になって、午後の2時から夜の10時まで同じ姿勢を保ったままでいるというのだった。訪れた者は、タイヤの山に分け入り、そこで動かないでいる彼らに触ったり揺り動かしたり、また別の者はお菓子など食べ物を口に入れたりしたが、彼らはそういう働きかけには一切応じないで同じ姿勢を保ち続けた。わたしは、タイヤの山に分け入り、一巡したが、タイヤの上を歩いたり跨いだりして結構疲れた。
窓を開け放って、暖房も利いてないところに長時間同じ姿勢でいて、生理現象をどう処理したのか、心配になって後で聞いてみたら、老人用のおむつを使ったということだった。彼らの話では、その生理現象を含めて、身体の反応は想像以上のものだったいう。彼らの一人は内蔵の運動の激しさをまざまざと感じさせられたといっていた。自らに自らの身体を突きつけることで、彼らはそれ以前に感じたこともないものを感じ取ったに違いない。訪れた者は、労ったり、悪さをしたり、またおろおろした気持ちになったり、タイヤにまみれ戯れたりして、彼らに近づこうとするが、立場が違うということで拒絶される。それを企画した者と訪れる者と、その立場の違いで、その場での彼らとは違う存在であること思い知らされることになる。そこには「異なる身体」があった。彼らは拒絶を実現するという形で表現を完遂させたとでも言ったらいいのであろう。
2年生の大原 剛志君、小崎 亜衣さん、高橋 亮太君、橋 真雪さん、冨貴塚 悠太君、山本 圭太君たちの展示作品「world wide wave & the wall」は、校庭に4メートル5メートル8メートルの両面がスクリーンになっている大きな箱を作って、相対する4メートル5メートルのスクリーンに箱の内部が延長されていくような錯覚を持つ映像を外側から投射して、訪れた人は箱の中で見るという仕掛けになっていた。箱の中に入ると、両側に箱の内部が延長したような遠近感を取ったアニメーションが映写されていた。女性がこちらに向かって歩いてくると、スクリーン断面で身体がスキャンされたように、肉の断片になって消えて行く。とするうちに、その女性のいる空間が渦巻き上に回転して方形を重ねたアニメーションに代わり、次に光の点滅になり、箱内部の延長の実写になって数人の男女が脚立を立てて壁に絵の具を塗ったりする、というような映像が繰り返し映写されるのだった。スクリーンが大きいから視覚的に引き込まれる。感動するとかうっとりするとかということはないが、気分は高揚する。多分、これを作った彼には企画を考え、実際に箱を制作する過程で、どんどん気分が高揚して行き、映写の段階でその高揚が頂点に達したものと思う。わたしはその箱を訪れた者として、その高揚した気分を分け与えられたと感じたのだった。
「表現」というものの様相が変わりつつあると思う。少なくとも、受け手が参加することを要請されている。受け手はただ受け止めるだけに感覚を働かせるのではなく、積極的に全身的に働かせることになる。つまり、その作品を訪れた者がそこでは作品を装置として主体的にそれなりに表現してしまうといえないだろうか。この辺りのことは、更に考えてみたい。